
|
電離層の活動は一般的に我が国の属する中緯度付近では、春秋に大きく、夏冬に低い。日周的には、地方時13時頃最大となり、夜明け前に最小となる。
(3)電離圏の影響
電離層を電磁波が通過する際の影響としては、
(1)伝搬速度の変化による影響と(2)電波の屈折による伝搬経路の変化による伝搬時間の増加による影響が考えられる。
これらは、伝搬媒質の屈折率の違いにより生じる位相速度、群速度の変化に起因するものである。GPSの測距信号(L1:1575.42 MHz;L2:1227.6MHz)での上記(2)の伝搬経路の変化量は、電離層の場合、1?以下でありほぼ無視できる量と考えられる。一方(1)の伝搬速度に対する影響は、第1次近似で次式で定量的に評価できる。
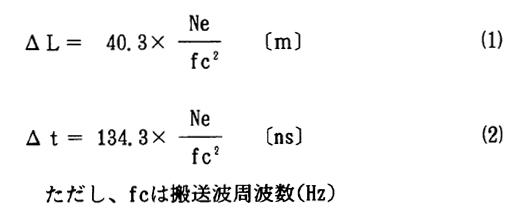
Neの値は、電離層の状況により複雑に変化するが、天頂方向で、太陽活動度極大期昼間には1×10 18[elec./m2]以上に、逆に極小期夜間では1×10 16[elec./m2]以下にまで低下する。
このためL1波では、最大20m程度(仰角30度では2倍、15度では3倍)の誤差要因となる。
GPS衛星からは、電離層遅延の実時間補正のため、L1・L2の2周波で信号が送られているが、これは、上記電離層遅延が搬送波周波数に対して分散性を有することを利用したもので、(1)、(2)式からNeが、
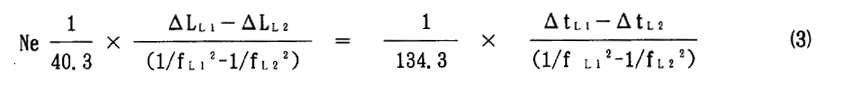
として推定でき、これを用いて遅延時問の補正が可能である。
しかしながら、L2波は通常、一般利用者には非公開のP−code信号でのみで変調(精密相対測位受信機ではトcodeを用いているものが多々ある)されており、L1の1周波利用者には、電離層補正のためのモデルが航法データの中で放送されている。
(4)電離層全電子数の実測
当所では、数年前(1988年)にGPSを用いた原子時の国際比較の電離層遅延補正を主目的として、GPS衛星の2周波(L1,L2)P−code信号を用いた電離層遅延測定装置を開発した。これは、2周波P−code信号の相関を利用したもので、コードレス受信機の1種である。P−codeクロックレート(10.23MHz)、コードレス方式であるため、測定精度としては、1〜2ns
前ページ 目次へ 次ページ
|

|